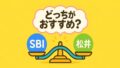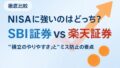はじめに
はじめて証券口座を作るとき、検索上位や口コミで必ず目に入るのが SBI証券 と 楽天証券。どちらも新NISAに完全対応しており、国内株・米国株・投資信託・ETFをワンストップで扱える総合力を持っています。
一方で、得意分野の方向性が違うため、あなたの投資スタイルによって“最適解”は変わります。
- SBI証券:外国株やETFまで含めて幅広く投資したい、分析ツールもガッツリ使いたい人に向く
- 楽天証券:楽天ポイントや楽天カード積立を活かし、手間なく・気軽に積立投資を始めたい人に向く
僕自身は両方の口座を持ち、用途で使い分けています。本記事では体験ベースのリアルな視点で、手数料/NISA/外国株/投信ラインナップ/ツール/サポート/デメリットまで“全部乗せ”で比較します。
超要約
- 初心者で「まず1口座」なら? → 楽天証券(ポイント投資・アプリの分かりやすさ・設定の簡単さ)
- 慣れてきて、米国以外も視野に入れたい/分析も重視 → SBI証券(外国株の広さ・ツールの強さ)
- 最適解 → 両方開設して使い分け(ポイント投資=楽天、メイン運用=SBI という二刀流が強い)
比較表(要点だけ先取り)
| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|
| 口座規模・安心感 | 国内トップ級の規模感 | 国内上位。楽天経済圏シナジー |
| 新NISA | 完全対応 | 完全対応 |
| 国内株(NISA) | 売買手数料無料 | 売買手数料無料 |
| 米国株(NISA) | 売買手数料無料 | 売買手数料無料 |
| 外国株の幅 | 米国に加え欧州・アジア等にも広く対応(※国別の取扱いは変更され得る) | 米国中心 |
| 投資信託 | 約2,600本クラス(低コスト指数系も充実) | 約2,600本クラス(人気インデックス一通りOK) |
| 為替 | 住信SBIネット銀行連携などでコスト低減しやすい | 楽天銀行連携などでコスト低減しやすい |
| ポイント投資 | Vポイント・Pontaに対応 | 楽天ポイントに対応 |
| クレカ積立 | 三井住友カード (ポイント還元あり) | 楽天カード (ポイント還元あり) |
| ツール/アプリ | HYPER SBI 2(高機能・多機能) | iSPEED(直感的・初心者向け) |
| サポート体感 | 利用者が多く混雑感あり | 比較的つながりやすい印象 |
※各社の手数料・取扱銘柄・サービスは変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
以降、この表の各項目を具体例・体験談・注意点と合わせて深掘りします。
手数料:ゼロにできる範囲と“落とし穴”
NISA口座の売買手数料
- SBI/楽天ともに:国内株・米国株は売買手数料無料
→ NISA枠内での売買はコストゼロ運用が可能。初心者にとって大きな安心材料です。
通常口座(特定口座)での売買
- 国内株の定額プラン:少額〜中額の売買回数が多い人向け。
- 1回ごとの従量プラン:売買頻度が少ない・金額が大きめの人向け。
→ 月の取引パターンでどちらが得かが変わるため、自分の売買習慣で最適化するのがコツ。
信用取引(1日信用など)
- SBI/楽天ともに:「1日信用」を選べば手数料ゼロ(※当日返済前提/一部銘柄を除く)。
- 注意:持ち越すとコスト発生(金利・貸株料など)。デイトレ前提なら問題ナシ、うっかり持ち越しだけ注意。
為替コスト(米ドル)
- SBI:住信SBIネット銀行連携などで低コスト運用がしやすい構造。
- 楽天:楽天銀行等との連携策あり。
→ 米国株の積立・ETF投資では、両社とも実質的な負担を抑えられる手当てが用意されています。
落とし穴メモ
- 「無料アピール=完全に何もかからない」ではありません。プランや条件に**例外(対象外銘柄、金利、貸株料、為替)**があるため、取引前に“その場の条件”を一度だけ確認しましょう。ルールに沿えばコストは抑えられます。
NISA:両社とも“強い”。でも得意分野が違う
- SBI証券
- 米国ETFや個別株まで幅広い商品をNISAで扱いやすい。
- 「将来、米国以外の海外株も買いたい」など発展性を重視する人と相性◎。
- 楽天証券
- 楽天ポイントをそのまま投資に回しやすい。
- アプリやUIがわかりやすく、最初の一歩が踏み出しやすい。
ケース別の使い分け
- 積立メイン・家計連動で手堅く → 楽天(ポイント&カード積立の気軽さ)
- ETF・外国株も取り込みたい長期設計 → SBI(ラインナップと拡張性)
外国株:投資の“自由度”はSBI、シンプルさは楽天
- SBI証券
- 米国に加えて欧州・アジアなどにも対応(※国・市場の取扱いは時期により変更があり得るため、その時々の最新情報を要確認)。
- ADRの選択肢も広く、分散の自由度が高い。
- 楽天証券
- 米国株中心。
- それでも主要ETF・個別の人気銘柄は十分にカバー。米国一本でいくなら不足感は少ない。
投資プラン別の相性
- 全世界へ広げたい:SBI(将来的な選択肢の広さが効く)
- 米国に集中する:楽天(UIがシンプルで迷いにくい)
投資信託:本数は同規模、使い勝手で選ぶ
- SBI・楽天ともに約2,600本クラスの取扱い。
- 低コストの**インデックス系(全世界・S&P500 など)**は両社で購入可。
- 選ぶ際に見るべきは、信託報酬・純資産・トラッキング差・指数の違い。
→ 迷ったら「超低コスト・純資産の安定感・指数が自分の方針と合うか」の3点でふるいにかけると失敗しにくい。
ポイント投資・クレカ積立:生活導線に馴染むのは楽天、カード選択肢はSBIも強い
- 楽天証券
⇒楽天ポイントをそのまま投資へ。
⇒楽天カード積立で自動的にポイントが貯まり、“気づいたら投資額が増えている”体験が作りやすい。 - SBI証券
⇒Vポイント・Pontaポイントなどに対応。
⇒三井住友カードとの連携で、積立時に還元が受けられる。
⇒生活の軸が「楽天」ではない人でも、カード選択の自由度でポイント導入しやすい。
ツール&アプリ:機能のSBI、直感の楽天
- SBI|HYPER SBI 2
- マルチ画面、板発注、スピード注文、スクリーニング、テクニカル豊富。
- **“考える・分析する・組む”**人に刺さる。PCで腰を据えて使うイメージ。
- 楽天|iSPEED
- スマホ中心での完結度が高い。UIがわかりやすい。
- 初心者はもちろん、中級者でも日中の発注・チェックに十分。
僕の感覚
- 朝の寄り付き〜ザラバの瞬発力:軽快なUIの恩恵は大きい
- 引け後の振り返り&翌日の仕込み:SBIの分析機能が活きる
→ “取引はスマホ、設計はPC” という分業が最強。
サポート&口座開設のスムーズさ
- チャット応答
- 体感として楽天のほうが繋がりやすい時がある。
- SBIは規模ゆえに混みがちな時間帯もあるが、FAQの充実やコミュニティ情報が豊富。
- 口座開設の流れ
- オンライン本人確認でスムーズ。
- 銀行連携(SBIなら住信SBI、楽天なら楽天銀行)を後回しにしないほうが運用導線が整う。
- **特定口座(源泉徴収あり)**にしておくと、確定申告の手間が大幅に減る(初心者はこれ一択でOK)。
よくある“つまずき”と回避策
- NISAで何を買うか決められない
- 最初は超低コストの広く分散されたインデックスに寄せる。迷いが減り、継続しやすい。
- ポイント投資の還元だけで選んでしまう
- ポイントは“きっかけ”。商品性(コスト・指数)>ポイントの順で考える。
- 為替や手数料の“例外”を見落とす
- その日の発注画面の条件を1回だけ確認。癖づけで事故は防げる。
- ツールに慣れず手が止まる
- お試し少額で触り、テンプレを体に入れる。取引テンポが整えばミスも減る。
僕の使い分け(体験談)
- メイン運用=SBI
- 米国ETFや海外株まで守備範囲を広く取れる。
- HYPER SBI 2で前夜の仕込み〜条件チェックを“まとめて”行う。
- サブ運用=楽天
- 楽天ポイントを自動で投資に回す導線が作りやすい。
- 忙しい日でもスマホだけで完結でき、投資の“途切れ”を防げる。
結論(僕の型)
- 楽天で“勝手に積立される仕組み”を作る
- SBIで“考えて仕掛ける投資”を育てる
→ 生活×投資の両輪が回り続ける。
ケーススタディ:あなたはどっちタイプ?
A. はじめての投資/少額で積立中心
- 楽天を第一候補。ポイント→投資の習慣化が最速。
- 将来、ETFや個別株へ広げたくなったらSBIを追加。
B. すでに投信を続けており、米国以外も検討
- SBIで外国株の選択肢を確保。
- 投信積立やNISAもまとめてSBI化すると管理がシンプル。
C. 家族・夫婦で投資を始めたい
- 片方=楽天(生活導線でポイント投資)、もう片方=SBI(メインポートフォリオ)で役割分担。
ありがちな質問
Q1. NISAを始めるならSBIと楽天どっち?
A. どちらでも正解。ポイント重視なら楽天、商品幅・拡張性重視ならSBI。
Q2. 口座は両方作るべき?
A. 両方持ちは強い。ポイント投資×本格運用を両立できる。
Q3. 投信の“中身”は本当に同じ?
A. 同じインデックスでも運用会社・指数・信託報酬が違うことがある。コストと指数を確認。
Q4. 米国株だけで十分?
A. それも正解。米国中心のシンプル設計は続けやすい。一方、SBIは将来の地域分散にも対応しやすい。
Q5. どのタイミングで買えばいい?
A. タイミング当ては難しい。**積立(時間分散)**で“続ける設計”に寄せるのが王道。
Q6. ツールが難しそう…
A. 楽天アプリ:直感で操作。SBIツール:慣れるほど強い。最初は少額+テンプレ発注で習熟を。
Q7. 為替が怖い
A. 長期の積立なら為替の凸凹は吸収されやすい。両社とも為替コストを抑える施策あり。
Q8. 買付余力や入金の手間は?
A. 銀行連携(SBI↔住信SBI、楽天↔楽天銀行)を設定。最初に導線をつくるほど日々が軽くなる。
Q9. 乗り換えやすいのは?
A. 売却→現金化→移動はどちらも同様。“使い分け”前提がいちばんラク。
Q10. IPOやるなら?
A. 取り扱いは時期で差が出る。どちらにも口座があるとチャンスが増えるのは確か。
Q11. つみたて初心者に“致命的なNG”は?
A. 短期でやめること。値動きに一喜一憂せず、自動化・放置できる仕組みを最初に作る。
Q12. ポイント還元の具体的な%は?
A. 制度改定が起きがち。記事寿命を長くするため具体数値は控え、**“還元あり”**とだけ記載。最新は各社で確認を。
はじめ方(迷わない最短ルート)
- どちらか1口座(迷うなら楽天)をオンライン申込
- 銀行連携(楽天なら楽天銀行、SBIなら住信SBI)まで一気に設定
- NISA枠をつみたて用ファンド1〜2本に割り当て
- スマホにアプリを入れ、残高推移だけ毎月見る
- 投資に慣れたらSBIも開設して、ETF/海外株などを少額で試す
デメリット(正直に)
- SBI
⇒機能が多く、最初は複雑に感じる。
⇒サポートが混み合う時間帯も。 - 楽天
⇒外国株は米国中心で、選択肢の広さではSBIに一歩譲る。
⇒各種ポイント制度は改定リスクがある(だから数字を固定で書かない)。
まとめ:僕ならこう使う
- 最初の1口座:楽天証券で積立の仕組み化(ポイント&カードで“勝手に貯まる”状態へ)
- 2口座目:SBI証券で商品幅と分析力をプラス(ETFや海外株、チャート分析はSBIが心強い)